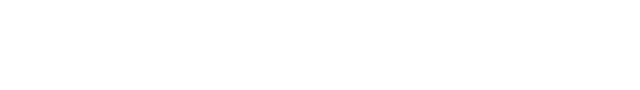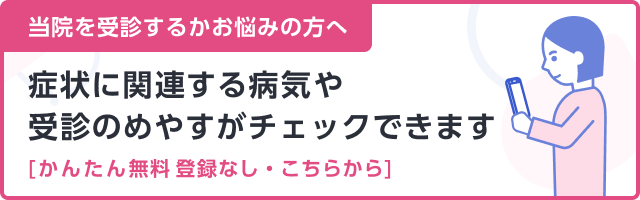パーキンソン病のデバイス補助療法(DAT: device aided therapy)
パーキンソン病の治療はL-ドパ製剤を中心とした薬による薬物療法とリハビリテーションが基本となります。
しかし、病状の進行に伴い、薬の効果が弱まり、薬の投与量が増えることによる副作用が問題となります。
薬の投与量が増えるほど薬の濃度が高く体が動きやすいon時間と、くすりの濃度が低く体が動かしにくいoff時間が出現してきます。
また、薬を服用する前に効果が切れるウェアリングオフ現象や薬の濃度が高くなり勝手に体が動くようなジスキネジアなどの副作用も出現しやすくなります。
そのため、病状が進行してきますと薬の濃度変化をなるべく起こさないように、L-ドパ製剤を少量ずつ頻回に服用する方法が選択される事が多くなります。
現在はこのような薬の服薬調整に加え、デバイス補助療法を用いることにより、これらの問題が軽減されることが期待されています。
主なデバイス補助療法として、①脳に電極を挿入して電気信号を送る脳深部刺激療法(DBS)、②ポンプとチューブで小腸に薬を持続的に注入するレボドパ/カルビドパ配合剤持続経腸療法(LCIG)があります。
脳深部刺激療法:DBS(Deep Brain Stimulation)
ドパミン放出の減少に伴う脳回路の異常を、電極からの電気信号によって回路を正常に機能させる治療。
off時間が改善され、薬の投与量・投与回数を減らすことができ、その結果ジスキネジアの発現が抑制され、安定した状態を24時間保つことができる。
治療ターゲットとして、視床下核、淡蒼球内節、視床腹中間核の3つがあり、症状などにより刺激部位が選択される。
・ 視床下核STN:subthalamic nucleus
最も一般的に用いられ、震え(振戦)、体が動かない(無動)、体が硬い(固縮)症状に対し効果が期待できる。
特にoff時間の症状改善に期待され、抗パーキンソン病薬の減量が期待出来る。
一方で精神症状、認知機能障害悪化の懸念が指摘されている。
・ 淡蒼球内節Gpi:globus pallidus internus
STNと同様の効果が期待出来るが、off時間の症状改善は困難で抗パーキンソン病薬の減量は期待できないが、認知機能症状への悪化が少ないとされる。
・ 視床腹中間核Vim:ventral intermediate nucleus
振戦に対して効果が期待されるが、他の運動症状の改善は乏しく、適応されるケースは限られる。
レボドパ/カルビドパ配合剤持続経腸療法:LCIG(Levodopa-carbidopa continuous infusion gel (LCIG) therapy)
ウェアリングオフ現象やジスキネジアが生じて十分な治療が困難となった場合に検討される。
ゲル状のレボドパ/カルビドパ配合剤を胃瘻から空腸に進めたチューブを経由して持続的に薬剤を注入する治療法。
持続的に薬剤を投与することから、薬の濃度を一定に保つ事が期待でき、体の動きが悪い時間(off時間)が短くなり、薬の濃度が急激に高くならないことからジスキネジアも軽減できる。
注意点は、夜間が使用できないため夜間は経口摂取で対応が必要なこと、朝の装着に介助者の補助が必要であること、胃瘻チューブの閉塞などのトラブルの問題がある。
* レボドパを24時間連続投与すると、効果を得るまでの投与量が増えやすくなります。一方で1日16時間投与では効果を得るまでの投与量が低下することが報告されています。また、血中ドパミン濃度は夜間低下し早朝に上昇する生理的日内変動があり、活動量が低い夜間の相対的過剰投与をさけるために夜間は使用しないこととなっています。